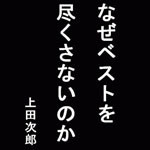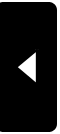2015年10月22日
バス釣りでバラシを減らす方法を考える
釣り人にとってバラシは大敵です。
魚をばらすことが好きな釣り人は皆無でしょう。
そのバラシをできるだけ回避するためのタックルセッティングを考えてみました。
その前に「バラシ」の語源が気になって調べてみましたが、これといったものは見つかりませんでした。
しかし辞書を引くと動詞として載っていました。
1 解体してばらばらにする。「機械を―・して修理する」「肉を―・す」
2 殺す。「裏切り者を―・す」
[補説]「殺す」と書いて「ばらす」と読ませることもある。
3 秘密などを人に知らせる。暴露する。あばく。「内紛を―・す」
4 不法に売り払う。また、売りとばす。「盗品を―・す」
5 針にかかった魚を釣り上げる途中で取り逃がす。「大物を―・してくやしがる」
僕は釣り人が作った専門用語かと思っていましたが、どうやら(比較的)一般的な言葉のようです。
・フックの刺さりが甘かった
・(フックはしっかりと刺さっていたが)糸ふけが発生してフックがフリーになった
ラインブレイクを除けば、この2つに帰結すると思います。
さらにこの2つ事象が発生する原因は、魚に起因するものとタックルに起因するものに二分できます。
こちらは魚に起因するものは少なく、タックルに起因するものが多いです。
しっかりとゲイプの奥までフッキングさせるためには『強いタックルを使う』こと『刺さりやすいフックを使う』
この2つだと思います。
刺さりやすい(≒細い)フックと伸びにくい(≒強い)フックは相反関係にあるので、妥協点は人によって違うと思います。
それに釣り方によっても妥協点は変わってきます。
僕の場合はワームの釣りはアタリがあってからアワセを入れるまでに間を置くことが多いので、強いもしくは大きいアワセを入れることができます。
そのため、フッキングにパワーや必要なゲイプの広いフックや、ネムリの入ったジグヘッドを好んで使います。
刺さりの良さだけを考えるとネムリが入っていない方が刺さりはよいのですが、フックの抜けにくさを考えるとネムリは効果的です。
またプラグの釣りは向こうアワセや体勢が整う前にアワセを入れることが多いので刺さりの良さを優先します。
(もちろん追いアワセは入れます)
トレブルフックはカルティバのST-31のバーブレスを使っています。
これは琵琶湖のバス釣りをする人の中では平均かそれよりも細い方だと思います。
なので、フックに合わせてタックルも比較的ライトなパワー(ライト〜ミディアム)を好んで使っています。
細軸のフックにヘビーなタックルだとフックが伸びちゃいますしね。
ランカーバスが釣れたときや根掛かりを外したときにはフックが(問題ない程度に)伸びていることもありますが、完全に伸ばされてばれたことは今のところありません。
(そもそもそんなに釣ってないですけどw)
まとめると、フックは刺さりやすさと伸びにくさ、外れにくさの相反する要素の妥協点を見出して、それに合ったタックル(ロッド、ライン)を使うことが大切だといえます。
ジャンプ、ヘッドシェイク、急な方向転換や突っ込み等、派手なアクションはバスフィッシングの醍醐味です。
しかし、自分が掛けたデカバスがこれらをやられるとヒヤヒヤもします。
「バレるなよ〜」
今でもデカバスがヒットするとこの言葉が出ます。
YouTubeで釣り動画を見ていても同じように口にするバスプロやプロガイドも多いです。
でも客観視すると弱気に見えて格好いいものではないので、最近は心の中で発するようにしています。
派手なアクションをいなして無事にキャッチできたときは、全く引かなかった魚をキャッチしたときよりも大きな喜びが得られます。

▲今までで一番派手に暴れられた魚(2007-09-15)
「ロッドを絶えず曲げ続けけていれば魚はばれないので、それを意識すること」と奥村部長と釣りをした時にアドバイスをもらいました。
関連記事:
★[琵琶湖]ガイド・5/9・ガイド初体験
[管釣り]嵐山FA・3/1・奥村部長から多くを学ぶ
魚をばらすことが好きな釣り人は皆無でしょう。
そのバラシをできるだけ回避するためのタックルセッティングを考えてみました。
その前に「バラシ」の語源が気になって調べてみましたが、これといったものは見つかりませんでした。
しかし辞書を引くと動詞として載っていました。
1 解体してばらばらにする。「機械を―・して修理する」「肉を―・す」
2 殺す。「裏切り者を―・す」
[補説]「殺す」と書いて「ばらす」と読ませることもある。
3 秘密などを人に知らせる。暴露する。あばく。「内紛を―・す」
4 不法に売り払う。また、売りとばす。「盗品を―・す」
5 針にかかった魚を釣り上げる途中で取り逃がす。「大物を―・してくやしがる」
僕は釣り人が作った専門用語かと思っていましたが、どうやら(比較的)一般的な言葉のようです。
そもそもなぜ魚をバラすのか?
・フックの刺さりが甘かった
・(フックはしっかりと刺さっていたが)糸ふけが発生してフックがフリーになった
ラインブレイクを除けば、この2つに帰結すると思います。
さらにこの2つ事象が発生する原因は、魚に起因するものとタックルに起因するものに二分できます。
ばらしの原因① フッキングが甘い
こちらは魚に起因するものは少なく、タックルに起因するものが多いです。
しっかりとゲイプの奥までフッキングさせるためには『強いタックルを使う』こと『刺さりやすいフックを使う』
この2つだと思います。
刺さりやすい(≒細い)フックと伸びにくい(≒強い)フックは相反関係にあるので、妥協点は人によって違うと思います。
それに釣り方によっても妥協点は変わってきます。
僕の場合はワームの釣りはアタリがあってからアワセを入れるまでに間を置くことが多いので、強いもしくは大きいアワセを入れることができます。
そのため、フッキングにパワーや必要なゲイプの広いフックや、ネムリの入ったジグヘッドを好んで使います。
刺さりの良さだけを考えるとネムリが入っていない方が刺さりはよいのですが、フックの抜けにくさを考えるとネムリは効果的です。
またプラグの釣りは向こうアワセや体勢が整う前にアワセを入れることが多いので刺さりの良さを優先します。
(もちろん追いアワセは入れます)
トレブルフックはカルティバのST-31のバーブレスを使っています。
これは琵琶湖のバス釣りをする人の中では平均かそれよりも細い方だと思います。
なので、フックに合わせてタックルも比較的ライトなパワー(ライト〜ミディアム)を好んで使っています。
細軸のフックにヘビーなタックルだとフックが伸びちゃいますしね。
ランカーバスが釣れたときや根掛かりを外したときにはフックが(問題ない程度に)伸びていることもありますが、完全に伸ばされてばれたことは今のところありません。
(そもそもそんなに釣ってないですけどw)
まとめると、フックは刺さりやすさと伸びにくさ、外れにくさの相反する要素の妥協点を見出して、それに合ったタックル(ロッド、ライン)を使うことが大切だといえます。
ばらしの原因② 糸ふけの発生
ジャンプ、ヘッドシェイク、急な方向転換や突っ込み等、派手なアクションはバスフィッシングの醍醐味です。
しかし、自分が掛けたデカバスがこれらをやられるとヒヤヒヤもします。
「バレるなよ〜」
今でもデカバスがヒットするとこの言葉が出ます。
YouTubeで釣り動画を見ていても同じように口にするバスプロやプロガイドも多いです。
でも客観視すると弱気に見えて格好いいものではないので、最近は心の中で発するようにしています。
派手なアクションをいなして無事にキャッチできたときは、全く引かなかった魚をキャッチしたときよりも大きな喜びが得られます。

▲今までで一番派手に暴れられた魚(2007-09-15)
「ロッドを絶えず曲げ続けけていれば魚はばれないので、それを意識すること」と奥村部長と釣りをした時にアドバイスをもらいました。
関連記事:
★[琵琶湖]ガイド・5/9・ガイド初体験
[管釣り]嵐山FA・3/1・奥村部長から多くを学ぶ
フックがしっかりと刺さっていて、ラインにテンションがかかっている状態であれば、魚はフックを外せません。
言いかえれば、ラインのテンションが抜けた状態(=糸ふけのの発生した状態)を作ってしまうとばれる可能性が一気に高まります。
ロッドを絶えず曲げ続けている状態を作れるかどうかにはロッド、リール、ラインにフックとその場で手にしているほぼ全ての釣り道具が関係してきます。
◆ロッド
曲がるロッド、かつ最後まで曲がりきらないロッドというのが僕が求めるスペックです。
曲がり切っちゃうロッドだと糸ふけは発生しませんが魚を寄せることができません。
こん棒のような曲がらないロッドだと魚の引きを吸収できずに糸ふけを発生しやすくなります。
それにそのようなロッドだと魚も派手に暴れますしね
テーパーは"曲がり"という点ではレギュラーテーパーやスローテーパーが優れていると思いますが、上手く曲げられるのであればファストテーパーでもデメリットにはならないと僕は思います。
◆リール
魚との距離が近ければ近いほど、バラシに対するリールの影響範囲は小さいと思います。
ラインには浮力があり、水中ではラインのたるみが発生します。
魚との直線距離が離れるほど、直線距離とラインの放出距離の誤差が大きくなります。
たるみがあるとフッキング時のパワーロスにもつながりますし、魚が暴れる際のラインの水中の抵抗も大きくなります。
ロングキャストで狙う場合はたるみを素早く回収できるハイギヤが有利だと思います。
ただあまりにハイギヤ過ぎると巻き心地が悪くなったり、リール自体のトルクが落ちる傾向にあるので注意が必要です。
ベイトリールの場合は6:1〜7:1前後のギヤ比が好みです。
(スプール径34mmのリールです)
またロッドを曲げ続けるためにはできるだけリールを巻き続ける必要があります。
そのためにも握りやすい(≒力を入れやすい)ハンドルノブを使うのも一つの手だと思います。
僕はダイワのリールが多いので、I'ZEのI型ラージノブを使っています。
ピクシーにつけているスケルトンのザイオンノブは力の入れやすさという点では全然ダメです。
でもこれは見た目重視で選んでいるので、自分の握力でリカバリします。
逆にスピニングリールの場合はラインも細く、ロッドもライトなためゴリ巻きすることはほとんどありません。
なのでスピニングはハイギヤが有利です。
それ以上に大事なのはドラグ性能です。
ストレスなくラインが放出されることはもちろん、ズルズルと出っ放しにならいないことが大事な性能だと思います。
設定値になるとドラグが作動するのは安価なリールでも担保されていますが、設定値以下になってもドラグが止まらないリールもあります。
具体例でいうとドラグを2kgに設定していれば、どのリールも張力が2kg以上になればドラグは作動します。
しかし一旦ドラグが作動し始めると、張力が2kg未満になってもドラグが作動しつづけてしまうリールが存在します。
求めるのは張力が2kg未満に戻ったらピタッと止まるドラグ性能です。
ドラグがズルズルになってしまうと途中でドラグを締めることになります。
ドラグを締めるとライン強度と設定値のバランスが破綻してラインブレイクに繋がりかねません。
個人的にはスプールをボールベアリングで支持する機構であれば問題ないと思っています。
◆ライン
ばらしにくさを考えた時のベストの選択はナイロンだと僕は思います。
逆にPEラインは伸びの少なさからばらしやすい印象があります。
それはあくまでラインの特性だけを考えた時の話で、実釣では使うロッドとの相性が大きく影響します。
ロングロッドやよく曲がるロッドであれば、PEラインの伸びの少なさをロッドがある程度リカバリしてくれると思いますし、逆にショートロッドやガチガチのロッドだと自分の腕まで使ってやりとりしないとバラす確率が高くなると思います。
一時期ボート釣りでよくやっていた跳ねジグヘッドはバラす確率が高い釣りでした。
エギングロッドのようなシャキッとしたロッドにPEラインという伸びの少ないタックルでやっていたので、魚の引きを上手く吸収できませんでした。
また吸収できないことで余計に魚を暴れさせてしまっていたようにも感じます。
その分ドラグを緩めにしてやり取りしていましたが、それでも他の釣りに比べるとキャッチ率の低い釣りでした。
管釣りではドラグを超ユルユルにしてばらしを低減させようとしている人も多くいますよね。
あまり格好よくはないので僕はやりませんが、理屈はわかります。
長々と書いてきましたが、タックルセッティング以外にもばらす要因はいくつかあります。
ルアー自体やフッキングの位置もばらしに影響があると思います。
(小さい割に重さのあるスピンテールジグなどはヘッドシェイクをされたときに外れやすいです)
それ以上にネックなのはデカい魚とのやり取りはデカい魚をヒットさせないと経験値が得られないことです。
どれだけ理屈を重ねても、現場での経験値がないとその場で冷静に対処することができずパニックになってしまいます。
僕はその経験値が少ないので、ロジックでそれを少しでも補おうという考え方です。
もちろんひとり一人考え方は違うと思いますし、僕自身も今後は違うことをいっているかもしれません。
釣りに行かなくても、このように楽しめるのが釣りという趣味の素晴らしいところだと思います。
言いかえれば、ラインのテンションが抜けた状態(=糸ふけのの発生した状態)を作ってしまうとばれる可能性が一気に高まります。
ロッドを絶えず曲げ続けている状態を作れるかどうかにはロッド、リール、ラインにフックとその場で手にしているほぼ全ての釣り道具が関係してきます。
◆ロッド
曲がるロッド、かつ最後まで曲がりきらないロッドというのが僕が求めるスペックです。
曲がり切っちゃうロッドだと糸ふけは発生しませんが魚を寄せることができません。
こん棒のような曲がらないロッドだと魚の引きを吸収できずに糸ふけを発生しやすくなります。
それにそのようなロッドだと魚も派手に暴れますしね

テーパーは"曲がり"という点ではレギュラーテーパーやスローテーパーが優れていると思いますが、上手く曲げられるのであればファストテーパーでもデメリットにはならないと僕は思います。
◆リール
魚との距離が近ければ近いほど、バラシに対するリールの影響範囲は小さいと思います。
ラインには浮力があり、水中ではラインのたるみが発生します。
魚との直線距離が離れるほど、直線距離とラインの放出距離の誤差が大きくなります。
たるみがあるとフッキング時のパワーロスにもつながりますし、魚が暴れる際のラインの水中の抵抗も大きくなります。
ロングキャストで狙う場合はたるみを素早く回収できるハイギヤが有利だと思います。
ただあまりにハイギヤ過ぎると巻き心地が悪くなったり、リール自体のトルクが落ちる傾向にあるので注意が必要です。
ベイトリールの場合は6:1〜7:1前後のギヤ比が好みです。
(スプール径34mmのリールです)
またロッドを曲げ続けるためにはできるだけリールを巻き続ける必要があります。
そのためにも握りやすい(≒力を入れやすい)ハンドルノブを使うのも一つの手だと思います。
僕はダイワのリールが多いので、I'ZEのI型ラージノブを使っています。
ピクシーにつけているスケルトンのザイオンノブは力の入れやすさという点では全然ダメです。
でもこれは見た目重視で選んでいるので、自分の握力でリカバリします。
逆にスピニングリールの場合はラインも細く、ロッドもライトなためゴリ巻きすることはほとんどありません。
なのでスピニングはハイギヤが有利です。
それ以上に大事なのはドラグ性能です。
ストレスなくラインが放出されることはもちろん、ズルズルと出っ放しにならいないことが大事な性能だと思います。
設定値になるとドラグが作動するのは安価なリールでも担保されていますが、設定値以下になってもドラグが止まらないリールもあります。
具体例でいうとドラグを2kgに設定していれば、どのリールも張力が2kg以上になればドラグは作動します。
しかし一旦ドラグが作動し始めると、張力が2kg未満になってもドラグが作動しつづけてしまうリールが存在します。
求めるのは張力が2kg未満に戻ったらピタッと止まるドラグ性能です。
ドラグがズルズルになってしまうと途中でドラグを締めることになります。
ドラグを締めるとライン強度と設定値のバランスが破綻してラインブレイクに繋がりかねません。
個人的にはスプールをボールベアリングで支持する機構であれば問題ないと思っています。
◆ライン
ばらしにくさを考えた時のベストの選択はナイロンだと僕は思います。
逆にPEラインは伸びの少なさからばらしやすい印象があります。
それはあくまでラインの特性だけを考えた時の話で、実釣では使うロッドとの相性が大きく影響します。
ロングロッドやよく曲がるロッドであれば、PEラインの伸びの少なさをロッドがある程度リカバリしてくれると思いますし、逆にショートロッドやガチガチのロッドだと自分の腕まで使ってやりとりしないとバラす確率が高くなると思います。
一時期ボート釣りでよくやっていた跳ねジグヘッドはバラす確率が高い釣りでした。
エギングロッドのようなシャキッとしたロッドにPEラインという伸びの少ないタックルでやっていたので、魚の引きを上手く吸収できませんでした。
また吸収できないことで余計に魚を暴れさせてしまっていたようにも感じます。
その分ドラグを緩めにしてやり取りしていましたが、それでも他の釣りに比べるとキャッチ率の低い釣りでした。
管釣りではドラグを超ユルユルにしてばらしを低減させようとしている人も多くいますよね。
あまり格好よくはないので僕はやりませんが、理屈はわかります。
長々と書いてきましたが、タックルセッティング以外にもばらす要因はいくつかあります。
ルアー自体やフッキングの位置もばらしに影響があると思います。
(小さい割に重さのあるスピンテールジグなどはヘッドシェイクをされたときに外れやすいです)
それ以上にネックなのはデカい魚とのやり取りはデカい魚をヒットさせないと経験値が得られないことです。
どれだけ理屈を重ねても、現場での経験値がないとその場で冷静に対処することができずパニックになってしまいます。
僕はその経験値が少ないので、ロジックでそれを少しでも補おうという考え方です。
もちろんひとり一人考え方は違うと思いますし、僕自身も今後は違うことをいっているかもしれません。
釣りに行かなくても、このように楽しめるのが釣りという趣味の素晴らしいところだと思います。
Posted by ueda at 07:00│Comments(6)
│ロジカルシンキング
この記事へのコメント
こんばんわ~(⌒‐⌒)
タックルセッティング、大切ですよね~!(;´д`)
一番いいのは、やはり日頃から慣れ親しんで馴染んだタックルが、一番強いですよね~(⌒‐⌒)
先週、知り合いの船で初のボートシーバスに出撃して来ましたけど、
タックルはフォーナインとCARDIFFのXUL(虹色竿)を持って行って、知り合いの皆さんに、相変わらすだね~!って、笑
流石に、CARDIFFで良い型のシーバスが来た時は、「あ、ヤベ~、引っ掛かった!」 と思ってロッドを煽ってました!笑
良く曲がりすぎる竿は、ショートバイトでもアワセも要らないくらいのアドバンテージがありますね~!(⌒‐⌒)ロッドが仕事してくれてバラシにくいし~!
CARDIFFで掛けるとただのメッキが、チビGTみたいでしたよ!笑
タックルセッティング、大切ですよね~!(;´д`)
一番いいのは、やはり日頃から慣れ親しんで馴染んだタックルが、一番強いですよね~(⌒‐⌒)
先週、知り合いの船で初のボートシーバスに出撃して来ましたけど、
タックルはフォーナインとCARDIFFのXUL(虹色竿)を持って行って、知り合いの皆さんに、相変わらすだね~!って、笑
流石に、CARDIFFで良い型のシーバスが来た時は、「あ、ヤベ~、引っ掛かった!」 と思ってロッドを煽ってました!笑
良く曲がりすぎる竿は、ショートバイトでもアワセも要らないくらいのアドバンテージがありますね~!(⌒‐⌒)ロッドが仕事してくれてバラシにくいし~!
CARDIFFで掛けるとただのメッキが、チビGTみたいでしたよ!笑
Posted by CARDIFF at 2015年10月25日 19:38
アモルファスウィスカーをググってたら貴方様のブログに行き着きました。
もしアモルファスウィスカーシリーズの事を知ってましたら一件教えて頂きませんか?
ロッドとグリップが分離するタイプの物があったと思うのですが、型式とか知ってませんか?
私の曖昧な記憶では2種類あったと記憶してます。
フリピング&ピッチング向きのコルクが細長いタイプ、貴方様が所持してる用なガンタイプの2種類あったと記憶してます。
もし、知ってましたら型式教えてください。
宜しくお願いします。
ブログ面白いですねw
もしアモルファスウィスカーシリーズの事を知ってましたら一件教えて頂きませんか?
ロッドとグリップが分離するタイプの物があったと思うのですが、型式とか知ってませんか?
私の曖昧な記憶では2種類あったと記憶してます。
フリピング&ピッチング向きのコルクが細長いタイプ、貴方様が所持してる用なガンタイプの2種類あったと記憶してます。
もし、知ってましたら型式教えてください。
宜しくお願いします。
ブログ面白いですねw
Posted by 引退して25年 at 2015年10月26日 00:16
>CARDIFFさん
こんにちは。
ボートシーバスに管釣りロッドとは…(^^;
柔らかい竿は針掛かりさせるの有利ですが、口が堅い魚だとフックを奥まで貫通させるのが難しいですよね~
その分細い軸のフックを使うと今度は伸びちゃうか心配だし。
でもデカい魚が掛からないような状況で、柔らかいロッドを使うのは僕も好きです。
こんにちは。
ボートシーバスに管釣りロッドとは…(^^;
柔らかい竿は針掛かりさせるの有利ですが、口が堅い魚だとフックを奥まで貫通させるのが難しいですよね~
その分細い軸のフックを使うと今度は伸びちゃうか心配だし。
でもデカい魚が掛からないような状況で、柔らかいロッドを使うのは僕も好きです。
Posted by ueda at 2015年10月26日 11:52
at 2015年10月26日 11:52
 at 2015年10月26日 11:52
at 2015年10月26日 11:52>引退して25年さん
はじめまして。
コメントありがとうございます。
僕はアモルファスウィスカーはこのAWB-602ULRしか持っていなくて、グリップとロッドが分離するオフセットハンドルがあったかどうかはわかりません。
最も固いロッドのAWB-762MHFはオフセットではなくてテレスコピックだったと記憶しています。
また、ワンランク下のカーボウィスカーシリーズや、そのあとに発売されたパワーメッシュファントム(PP)シリーズにはオフセットハンドルがありました。
友人の持っていたCWB-661MFや、僕が使っていたPP-661-4RBはオフセットハンドルでしたので、アモルファスウィスカーシリーズでも存在したかもしれません。
ダイワのパーツ検索システムで『AWB』で検索すると、アモルファスウィスカーシリーズの型番がヒットするので、そこから記憶を紐解いてもらうといいかもしれません。
もし思い出したら教えて下さい!
はじめまして。
コメントありがとうございます。
僕はアモルファスウィスカーはこのAWB-602ULRしか持っていなくて、グリップとロッドが分離するオフセットハンドルがあったかどうかはわかりません。
最も固いロッドのAWB-762MHFはオフセットではなくてテレスコピックだったと記憶しています。
また、ワンランク下のカーボウィスカーシリーズや、そのあとに発売されたパワーメッシュファントム(PP)シリーズにはオフセットハンドルがありました。
友人の持っていたCWB-661MFや、僕が使っていたPP-661-4RBはオフセットハンドルでしたので、アモルファスウィスカーシリーズでも存在したかもしれません。
ダイワのパーツ検索システムで『AWB』で検索すると、アモルファスウィスカーシリーズの型番がヒットするので、そこから記憶を紐解いてもらうといいかもしれません。
もし思い出したら教えて下さい!
Posted by ueda at 2015年10月26日 12:16
at 2015年10月26日 12:16
 at 2015年10月26日 12:16
at 2015年10月26日 12:16この度はご指導ありがとうございます。
貴方様のお陰で分かりました。
AWB-601MFでした。
型式見て25年前の記憶が蘇りましたw
グリップジョイント仕様と言えばよろしいのですか?
何故この様な話になったかと説明しますと、只今ヤフオクにてグリップを出品中でして、質問で直径何ミリのブランクが使用出来るか?との質問が来まして検索してた訳です。
型式は分かったのですが、何ミリかまでは不明なままですがw
バランスの悪い竿で、AWB-601MHSのグリップを注文して使ってた記憶があります。
型式が分かっただけでも一歩前進と言った所ですかね?
今後もちょくちょくブログ拝見したいと思います。
ご指導ありがとうございました。
貴方様のお陰で分かりました。
AWB-601MFでした。
型式見て25年前の記憶が蘇りましたw
グリップジョイント仕様と言えばよろしいのですか?
何故この様な話になったかと説明しますと、只今ヤフオクにてグリップを出品中でして、質問で直径何ミリのブランクが使用出来るか?との質問が来まして検索してた訳です。
型式は分かったのですが、何ミリかまでは不明なままですがw
バランスの悪い竿で、AWB-601MHSのグリップを注文して使ってた記憶があります。
型式が分かっただけでも一歩前進と言った所ですかね?
今後もちょくちょくブログ拝見したいと思います。
ご指導ありがとうございました。
Posted by 引退して25年 at 2015年10月27日 04:26
>引退して25年さん
こんにちは。
わざわざ返信ありがとうございます。
お役に立てたようでうれしいです!
確かに「AWB-601MF」で画像検索するとブランクとグリップが離れた画像がヒットしますね。
あの当時のダイワロッドは6ftまではガングリップが基本でしたが、一部には6'6"までもガングリップのモデルもあったような気がします。
(僕も記憶が蘇りました)
久々にアモルファスウィスカーのロッドを引っ張り出して使いたくなってきました!
今後もよろしくお願いいたします。
こんにちは。
わざわざ返信ありがとうございます。
お役に立てたようでうれしいです!
確かに「AWB-601MF」で画像検索するとブランクとグリップが離れた画像がヒットしますね。
あの当時のダイワロッドは6ftまではガングリップが基本でしたが、一部には6'6"までもガングリップのモデルもあったような気がします。
(僕も記憶が蘇りました)
久々にアモルファスウィスカーのロッドを引っ張り出して使いたくなってきました!
今後もよろしくお願いいたします。
Posted by ueda at 2015年10月27日 13:32
at 2015年10月27日 13:32
 at 2015年10月27日 13:32
at 2015年10月27日 13:32<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。 |



 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト