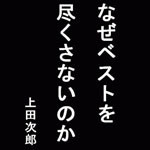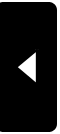2016年09月09日
沖縄遠征 離島でルアーフィッシング 16-09-04/平安座島-ボート
沖縄に釣り旅行に行ってきました。
LCCを使った2泊3日の旅行の中日(なかび)にボートをチャーターしてミーバイ(沖縄のハタ類の総称)を釣ってきました。

ボートをチャーターしたのは那覇から北東に40kmの距離にある平安座島(へんざじま)の海風(うみかぜ)です。
沖縄のシーカヤック&ルアーフィッシング 海風
ホテルを那覇市内にとっていたので、もっと近場がよかったのですが、近隣の釣り船屋さんはGT(ジャイアントトレバリー)やキハダマグロ等のガチの釣り物だったり、ライトゲームでも安くない価格設定のお店ばかりでした。
その点、海風は半日(7:00-12:00/12:30-17:30)で25,000円(最大3人まで)、一日(7:00-17:00)でも45,000円とチャーターにしては安価だったので、こちらでお願いしました。
・ボートエギング
・鳥山ナブラゲーム
・五目ライトゲーム
・タマンゲーム
釣り物も豊富で4つのメニューがありました。
どれも魅力で決められなかったので電話で相談したところ、「今の時期は五目ライトゲームがオススメ!」ということだったので、それの午前便でお願いしました。
キャプテンの坂本さんは知識や釣り方のレクチャーはもちろん、釣れた魚の扱いもスゴく丁寧でした。
また沖縄に行くことがあれば、次も海風・坂本さんにお世話になりたいです。
> ロッドはバスロッド(ML~M)、シーバスロッド(L~ML)の6~7ftが使いやすいでしょう。
> 根に潜る魚が多いので比較的バットパワーがあり一気に根から魚を引き離すことの出来るロッドが理想です。
> ラインはPE1号前後、リーダーはフロロカーボンの20LB前後をロッドの長さに合わせて1ヒロ(約150cm)を
> FGノット、PRノットなどで結束して下さい。
ホームページにはこのような記載があったので、メインはJetSetter-71S + 04 セルテート 2500R、サブでJetSetter-60C + アルファス SV 105SHを持ち込みました。

僕の持っているジェットセッターは2本とも仕舞寸法が50cm未満なので、機内に持ち込むことができます。
*だいたいどの航空会社でも55cmが機内に持ち込める最大サイズです。
パックロッドでもそれを超えてしまうと預ける必要があるのでご注意ください
今回はノースフェイスのBCダッフルを持っていったので、ジェットセッターに付属のロッドケースごとバッグの中に放り込んで機内に持ち込みました。
(バッグの中に斜めに入れるという技を使うともうちょっと長いロッドでも機内に持ち込めます)
関連記事:世界一周にも耐えるノースフェイス・BCダッフル
ラインはセルテートにはPE1号 + フロロ5号、アルファス SVにはPE0.8号 + フロロ4号をセットしました。
ルアーはワームがメイン。
本当はシャローでプラグを使って釣りたいところですが、台風が沖縄本島を直撃していない影響でまだまだ水温が高くシャローは壊滅的だということで今回は諦めました。
ワームのリグは14~18gのテキサスリグ。
ルアーは甲殻類系ならなんでもいいけど、バス用はフグやベラに食いちぎられて直ぐに使い物にならなくなるということだったので、今回はキャプテンの坂本さんのルアーを使わせてもらいました。
(ソフトルアー、シンカーとワームフックは別途500円で使い放題でした)

この日は針持ちのいいマグロのエビング用のワームをカットして使いました。
海風のある平安座島は沖縄本島の東側に位置する離島です。
離島ながら海中道路(全長5kmに及ぶ堤防道路)でつながっているので、船に乗ることなく気軽に行くことができます。

▲帰りに上空から撮影
狙ったのは島の周辺の水深20mから12~13mへかけ上がる根のポイント。
そこをシーアンカーで流しながら、かけ上がりに潜むミーバイを筆頭とした根魚を狙います。
釣り方はテキサスリグのリフト&フォールです。
といってもブラックバスのそれとは全然違いました。
まずフルキャストしたテキサスリグをフリーフォールで底まで落とし、そこからエギングばりのシャクリで4、5回リフト、そのあとはカーブフォールで再び底を取ります。
アタリはシャクリ(リフト)の途中か着底直後に「ゴン!」と出ることが多かったです。
当日は7時に港で待ち合わせて、7時半の出船でした。

出港前にタックルとドラグのチェックしてもらいましたが、JS-71Sはこの釣りにはバッチリだけどマイクロタッチことJS-60Cは厳しそうとのこと。
同行のゼネコン氏はこの旅行に合わせてシマノのトラスティック S610Lを購入。
そっちはちょっと柔らかいけどまぁなんとかなりそうということでした。
関連記事:トラスティック(Trastick)S610LとストラディックCI4+(STRADIC CI4+)C2500HGS(ゼネコンGO)
ドラグはラインの限界近くまでガチガチに締めました。
根に入られるとそこまで大きくないサイズでも引きはがすことはできないので、根に入られないようにすることが大切とのこと。


最初に入ったのは平安座島の南に位置する浜比嘉島(はまひがじま)のリーフ内にある根。
LCCを使った2泊3日の旅行の中日(なかび)にボートをチャーターしてミーバイ(沖縄のハタ類の総称)を釣ってきました。

ボートをチャーターしたのは那覇から北東に40kmの距離にある平安座島(へんざじま)の海風(うみかぜ)です。
沖縄のシーカヤック&ルアーフィッシング 海風
ホテルを那覇市内にとっていたので、もっと近場がよかったのですが、近隣の釣り船屋さんはGT(ジャイアントトレバリー)やキハダマグロ等のガチの釣り物だったり、ライトゲームでも安くない価格設定のお店ばかりでした。
その点、海風は半日(7:00-12:00/12:30-17:30)で25,000円(最大3人まで)、一日(7:00-17:00)でも45,000円とチャーターにしては安価だったので、こちらでお願いしました。
・ボートエギング
・鳥山ナブラゲーム
・五目ライトゲーム
・タマンゲーム
釣り物も豊富で4つのメニューがありました。
どれも魅力で決められなかったので電話で相談したところ、「今の時期は五目ライトゲームがオススメ!」ということだったので、それの午前便でお願いしました。
キャプテンの坂本さんは知識や釣り方のレクチャーはもちろん、釣れた魚の扱いもスゴく丁寧でした。
また沖縄に行くことがあれば、次も海風・坂本さんにお世話になりたいです。
タックル
> ロッドはバスロッド(ML~M)、シーバスロッド(L~ML)の6~7ftが使いやすいでしょう。
> 根に潜る魚が多いので比較的バットパワーがあり一気に根から魚を引き離すことの出来るロッドが理想です。
> ラインはPE1号前後、リーダーはフロロカーボンの20LB前後をロッドの長さに合わせて1ヒロ(約150cm)を
> FGノット、PRノットなどで結束して下さい。
ホームページにはこのような記載があったので、メインはJetSetter-71S + 04 セルテート 2500R、サブでJetSetter-60C + アルファス SV 105SHを持ち込みました。

僕の持っているジェットセッターは2本とも仕舞寸法が50cm未満なので、機内に持ち込むことができます。
*だいたいどの航空会社でも55cmが機内に持ち込める最大サイズです。
パックロッドでもそれを超えてしまうと預ける必要があるのでご注意ください
今回はノースフェイスのBCダッフルを持っていったので、ジェットセッターに付属のロッドケースごとバッグの中に放り込んで機内に持ち込みました。
(バッグの中に斜めに入れるという技を使うともうちょっと長いロッドでも機内に持ち込めます)
関連記事:世界一周にも耐えるノースフェイス・BCダッフル
ラインはセルテートにはPE1号 + フロロ5号、アルファス SVにはPE0.8号 + フロロ4号をセットしました。
ルアーはワームがメイン。
本当はシャローでプラグを使って釣りたいところですが、台風が沖縄本島を直撃していない影響でまだまだ水温が高くシャローは壊滅的だということで今回は諦めました。
ワームのリグは14~18gのテキサスリグ。
ルアーは甲殻類系ならなんでもいいけど、バス用はフグやベラに食いちぎられて直ぐに使い物にならなくなるということだったので、今回はキャプテンの坂本さんのルアーを使わせてもらいました。
(ソフトルアー、シンカーとワームフックは別途500円で使い放題でした)

この日は針持ちのいいマグロのエビング用のワームをカットして使いました。
ポイントと釣り方
海風のある平安座島は沖縄本島の東側に位置する離島です。
離島ながら海中道路(全長5kmに及ぶ堤防道路)でつながっているので、船に乗ることなく気軽に行くことができます。

▲帰りに上空から撮影
狙ったのは島の周辺の水深20mから12~13mへかけ上がる根のポイント。
そこをシーアンカーで流しながら、かけ上がりに潜むミーバイを筆頭とした根魚を狙います。
釣り方はテキサスリグのリフト&フォールです。
といってもブラックバスのそれとは全然違いました。
まずフルキャストしたテキサスリグをフリーフォールで底まで落とし、そこからエギングばりのシャクリで4、5回リフト、そのあとはカーブフォールで再び底を取ります。
アタリはシャクリ(リフト)の途中か着底直後に「ゴン!」と出ることが多かったです。
前半戦 リーフ内側のポイント
当日は7時に港で待ち合わせて、7時半の出船でした。

出港前にタックルとドラグのチェックしてもらいましたが、JS-71Sはこの釣りにはバッチリだけどマイクロタッチことJS-60Cは厳しそうとのこと。
同行のゼネコン氏はこの旅行に合わせてシマノのトラスティック S610Lを購入。
そっちはちょっと柔らかいけどまぁなんとかなりそうということでした。
関連記事:トラスティック(Trastick)S610LとストラディックCI4+(STRADIC CI4+)C2500HGS(ゼネコンGO)
ドラグはラインの限界近くまでガチガチに締めました。
根に入られるとそこまで大きくないサイズでも引きはがすことはできないので、根に入られないようにすることが大切とのこと。


最初に入ったのは平安座島の南に位置する浜比嘉島(はまひがじま)のリーフ内にある根。
本当はリーフの外の方が大型が釣れるのですが、リーフの外は沖縄本島をかすめていった台風12号の影響でうねりが残っていたので、内側のポイントを選択しました。
根から100m近く離れたところでボートの体勢を整えて、シーアンカーを使って根に向かって流します。
まずはキャプテンの坂本さんがJS-71Sを使って釣り方のレクチャー。
一投目でバイトが何回かあったので活性は低くないようです(^^)
ファーストヒットはゼネコン氏。
続いて僕にも南国っぽい魚がヒットします。

根に近づくとアタリが増えて、根のトップに来ると逆にアタリがなくなる感じ。
またトップを過ぎて根のかけ下がりでもアタリはありますが、かけ上がりに比べるとアタリの数は相当少ないです。
やっぱり潮の当たっている面の方が魚にとって快適なんでしょうね。

この日は大潮明けの中潮。
潮の流れが速く1キャストで4~5回しか底が取れません。
またテキサスの沈むスピードと船の流されるスピードがシンクロしていて、フリーフォールではラインの弛みを見ているだけでは底が取りにくい状況でした。
確実に底を取るためにはフォール中のラインに波紋が出ているかどうか、もしくはラインが手前側に弛むかどうかを注視する必要があります。
魚がそんなにスレていないので、そこまでしなくても充分に釣れるんですが、性格的にどうしても…。
潮の影響で1キャストで探る回数が少ないのと同様に、ひと流しで探れるのも4~5回がいいところです。
そして魚がヒットしちゃうとその間はまた流されるので、釣りをしている時間は半分くらいだったかもしれません。
そんな感じで入れ食いを堪能していると潮止まりの影響で急に反応がなくなってきました。
キャプテンからの提案でこのタイミングで移動することに。
風も収まってきたことと、潮は沖から動き始めることから、思い切ってリーフの外に出ることにしました。
先ほどのポイントから15分ほど走り、沖の根に入りました。

ポイントの地形・水深や狙い方は先ほどと同じですが、底の形状が複雑なので注意しないと根がかりする可能性が高いとのこと。
根がかりを避けるためにも、シャクリの回数を10回くらいまで増やした方がいいとキャプテンからアドバイスがありました。
また底が複雑ということは根がかり同様に魚に根に潜られる危険性も高まるので注意が必要です。
最初はなかなかアタリが出ませんでしたが、潮が走り始めると同時にゼネコン氏にビッグバイト!
買ったばかりのトラスティックがブチ曲がり、ギチギチに締めたドラグをあざ笑うかのようにラインが引き出されます。
しばらく格闘するも根に入られて動かなくなってしまい万事休すかと思いましたが、上手くテンションを緩めて待っていると魚が動きロッドティップに変化が出しました。

そのタイミングで強引に引っ張ることで上手く根から剥がすことができ、無事にネットイン!
釣れたのは60cm弱・2kgの見事なアカジンミーバイ(スジアラ)でした。
アカジンミーバイはハタの仲間です。
シルエットはどう見ても根魚なのですが、ヒット後の引きは根魚のそれではなくスピードとパワーを兼ね備えた青物のような引きでした。
ちなみに多くの魚は着底の直前か直後にアタリが出るのですが、このアカジンミーバイは遊泳力が高いので、ハタ類のくせにシャクリの途中で食ってくるそうです。
これまで釣った魚は全てリリースしていましたが、この魚はキャプテンに献上。
釣りのガイドと漁師も兼ねているので、漁協に持っていくそうです。
僕もあの引きを体感したいですし、超高級魚を釣り上げたいという欲もあります。


今まで以上に丁寧に釣り込みますが、僕にヒットするのはヤガラやオジサンなど多様な魚種。笑
なかなか釣る機会のない魚ばかりなので、何が釣れても楽しいのですがアカジンミーバイだけが釣れてくれません。
1回だけシャクリの途中に「ガツン」とバイトがありましたが、残念ながら根に入られてバレちゃいました…。
また底が複雑な影響か、リーダーの消耗も半端なく、船上で4~5回結び直すことになりました。
見かねたキャプテンが僕の倍くらいの速さでFGノットを組んでくれましたが、残念ながら期待に応えることはできず…。
逆にゼネコン氏は絶好調で45cmの2匹目のアカジンミーバイをゲット!
先ほどよりも小ぶりでしたが、強烈な引きを堪能していました。
アカジンミーバイ以外の魚も引きは強く、やり取りしている最中は「デカいかも!」と思わせてくれるのですが、姿を見るとイメージよりも10cm以上も小さいサイズであることがほとんどでした。
どの魚も同サイズのブラックバスとは比べものにならない引きの強さです。
そんな感じで入れ食いを堪能し、11時半に沖上がり。


魚とのやり取りとリフト&フォールのシャクリで右腕がパンパンになってしまいました(^^;
この釣りはワームでアタリを取る釣りが好きな人にはたまらなく楽しい釣りだと思います。
タイミングによってはタマンことオキフエフキも釣れるそうですし、アカジンミーバイも4kgくらいまでは釣れるそうです。
(取れるかどうかは別にして…)
『もし自分がまたこの釣りをするなら…』という視点で振り返ってみます。
<タックル>
・ロッドは強めのエギングロッド
⇒ JS-71Sは自重が重く腕がパンパンになりました。軽いエギングロッドにすることでシャクリでの疲労度軽減と魚を止めるバットパワーに期待です。
・リールはハイギヤ+ロングハンドル
⇒ フッキング直後に魚に主導権を奪われないために。また大型魚の場合はポンピングが必須なのでその点でもハイギヤが有利だと思います。また引きの強さが半端ないのでハンドルは55mm以上のロングハンドル+丸型のノブがいいと思います(僕はRCSの50mmハンドル + T型ノブでした)。
・メインラインは1ランク太目(PE1.2号)
⇒ なんだかんだで4回ほど根がかりしました。その際にリーダーを失わないためにもライン強度をメインライン>リーダーにする必要があります。リーダーを5号(20LB)未満にすることは考えにくいのでメインラインを太くします。
・シンカーはタングステンを持参
⇒ キャプテンに借りたシンカーは鉛の中通しオモリでした。同じ重さならタングステンの方が小さいので、シャクリの跳ね具合、根がかりのしにくさ、キャストの飛距離とタングステンにアドバンテージがあります(ただし値段が数倍に…)。水深20m前後なら14g、18g、21gの3種類で対応できると思います。
<釣り方>
・アワセは小さく鋭くする
⇒ ワームを使ったブラックバスの釣りではストロークの大きなアワセを心がけていますが、今回はそれは逆効果でした。ストロークの大きなアワセ自体がダメなのではなく、アワセの後にラインを回収しないとファイトに入れないのがNGの要因です。魚に主導権を与えないためにも小さくて鋭いアワセ(+ハイギヤのリール)を心がけたいところです。
・バラした直後にルアーを回収しない
⇒ これはキャプテン指摘されるまで全く気付かない癖でした。フィッシュイーターは他の魚が食っているエサを狙っているため、また直ぐにヒットする確率が高いとのこと。「バラしたルアー=口から逃げたベイトフィッシュ」という認識ですね。確かに意識したらバラした直後に何回かヒットしました。
遠征釣行というと大げさに聞こえますが、LCC(ジェットスター)を上手く使えば、琵琶湖でバスガイドに乗るのと変わらないくらいの費用で普段とは別世界の釣りを満喫できます。
また、遠征や旅行の計画がない人もパックロッドを1本買うことで色々と行きたくなること間違いなしです。
僕がよく書くタキシード理論です。
> 「パーティーに呼ばれないから、タキシードを買わない」のではない
> 「タキシードを持っていないから、パーティーに呼ばれないのだ」
タキシードをパックロッドに置き換えると…
「遠征の予定がないから、パックロッドを買わない」のではない
「パックロッドを持っていないから、遠征の予定が立たないのだ」
遠征釣行に興味がある人はパックロッドとダッフルバッグを購入されることを強くおススメします。
関連記事:LCCを利用した格安釣り旅行のススメ
[パックロッドチャレンジ企画]現在の攻略状況(2016年9月現在)
1魚種目 : 鯉
2魚種目 : ブラックバス(スモールマウスバス)
3魚種目 : ニゴイ
4魚種目 : ナマズ
5魚種目 : ブラックバス(ラージマウスバス)
6魚種目 : ロウニンアジ(メッキ)
7魚種目 : マエソ
8魚種目 : クワガナー(コトヒキ)
9魚種目 : マングローブジャック(ゴマフエダイ)
10魚種目 : クロダイ(ナンヨウチヌ)
11魚種目 : イシミーバイ(カンモンハタ)
12魚種目 : ナガジューミーバイ(バラハタ)
13魚種目 : アカハタ
14魚種目 : アオヤガラ
15魚種目 : オジサン
16魚種目 : オキフエダイ
根から100m近く離れたところでボートの体勢を整えて、シーアンカーを使って根に向かって流します。
まずはキャプテンの坂本さんがJS-71Sを使って釣り方のレクチャー。
一投目でバイトが何回かあったので活性は低くないようです(^^)
ファーストヒットはゼネコン氏。
続いて僕にも南国っぽい魚がヒットします。

根に近づくとアタリが増えて、根のトップに来ると逆にアタリがなくなる感じ。
またトップを過ぎて根のかけ下がりでもアタリはありますが、かけ上がりに比べるとアタリの数は相当少ないです。
やっぱり潮の当たっている面の方が魚にとって快適なんでしょうね。

この日は大潮明けの中潮。
潮の流れが速く1キャストで4~5回しか底が取れません。
またテキサスの沈むスピードと船の流されるスピードがシンクロしていて、フリーフォールではラインの弛みを見ているだけでは底が取りにくい状況でした。
確実に底を取るためにはフォール中のラインに波紋が出ているかどうか、もしくはラインが手前側に弛むかどうかを注視する必要があります。
魚がそんなにスレていないので、そこまでしなくても充分に釣れるんですが、性格的にどうしても…。
潮の影響で1キャストで探る回数が少ないのと同様に、ひと流しで探れるのも4~5回がいいところです。
そして魚がヒットしちゃうとその間はまた流されるので、釣りをしている時間は半分くらいだったかもしれません。
そんな感じで入れ食いを堪能していると潮止まりの影響で急に反応がなくなってきました。
キャプテンからの提案でこのタイミングで移動することに。
風も収まってきたことと、潮は沖から動き始めることから、思い切ってリーフの外に出ることにしました。
後半戦 リーフ外側のポイント
先ほどのポイントから15分ほど走り、沖の根に入りました。

ポイントの地形・水深や狙い方は先ほどと同じですが、底の形状が複雑なので注意しないと根がかりする可能性が高いとのこと。
根がかりを避けるためにも、シャクリの回数を10回くらいまで増やした方がいいとキャプテンからアドバイスがありました。
また底が複雑ということは根がかり同様に魚に根に潜られる危険性も高まるので注意が必要です。
最初はなかなかアタリが出ませんでしたが、潮が走り始めると同時にゼネコン氏にビッグバイト!
買ったばかりのトラスティックがブチ曲がり、ギチギチに締めたドラグをあざ笑うかのようにラインが引き出されます。
しばらく格闘するも根に入られて動かなくなってしまい万事休すかと思いましたが、上手くテンションを緩めて待っていると魚が動きロッドティップに変化が出しました。

そのタイミングで強引に引っ張ることで上手く根から剥がすことができ、無事にネットイン!
釣れたのは60cm弱・2kgの見事なアカジンミーバイ(スジアラ)でした。
アカジンミーバイはハタの仲間です。
シルエットはどう見ても根魚なのですが、ヒット後の引きは根魚のそれではなくスピードとパワーを兼ね備えた青物のような引きでした。
ちなみに多くの魚は着底の直前か直後にアタリが出るのですが、このアカジンミーバイは遊泳力が高いので、ハタ類のくせにシャクリの途中で食ってくるそうです。
これまで釣った魚は全てリリースしていましたが、この魚はキャプテンに献上。
釣りのガイドと漁師も兼ねているので、漁協に持っていくそうです。
僕もあの引きを体感したいですし、超高級魚を釣り上げたいという欲もあります。


今まで以上に丁寧に釣り込みますが、僕にヒットするのはヤガラやオジサンなど多様な魚種。笑
なかなか釣る機会のない魚ばかりなので、何が釣れても楽しいのですがアカジンミーバイだけが釣れてくれません。
1回だけシャクリの途中に「ガツン」とバイトがありましたが、残念ながら根に入られてバレちゃいました…。
また底が複雑な影響か、リーダーの消耗も半端なく、船上で4~5回結び直すことになりました。
見かねたキャプテンが僕の倍くらいの速さでFGノットを組んでくれましたが、残念ながら期待に応えることはできず…。
逆にゼネコン氏は絶好調で45cmの2匹目のアカジンミーバイをゲット!
先ほどよりも小ぶりでしたが、強烈な引きを堪能していました。
アカジンミーバイ以外の魚も引きは強く、やり取りしている最中は「デカいかも!」と思わせてくれるのですが、姿を見るとイメージよりも10cm以上も小さいサイズであることがほとんどでした。
どの魚も同サイズのブラックバスとは比べものにならない引きの強さです。
そんな感じで入れ食いを堪能し、11時半に沖上がり。


魚とのやり取りとリフト&フォールのシャクリで右腕がパンパンになってしまいました(^^;
この釣りはワームでアタリを取る釣りが好きな人にはたまらなく楽しい釣りだと思います。
タイミングによってはタマンことオキフエフキも釣れるそうですし、アカジンミーバイも4kgくらいまでは釣れるそうです。
(取れるかどうかは別にして…)
反省点(アドバイス)
『もし自分がまたこの釣りをするなら…』という視点で振り返ってみます。
<タックル>
・ロッドは強めのエギングロッド
⇒ JS-71Sは自重が重く腕がパンパンになりました。軽いエギングロッドにすることでシャクリでの疲労度軽減と魚を止めるバットパワーに期待です。
・リールはハイギヤ+ロングハンドル
⇒ フッキング直後に魚に主導権を奪われないために。また大型魚の場合はポンピングが必須なのでその点でもハイギヤが有利だと思います。また引きの強さが半端ないのでハンドルは55mm以上のロングハンドル+丸型のノブがいいと思います(僕はRCSの50mmハンドル + T型ノブでした)。
・メインラインは1ランク太目(PE1.2号)
⇒ なんだかんだで4回ほど根がかりしました。その際にリーダーを失わないためにもライン強度をメインライン>リーダーにする必要があります。リーダーを5号(20LB)未満にすることは考えにくいのでメインラインを太くします。
・シンカーはタングステンを持参
⇒ キャプテンに借りたシンカーは鉛の中通しオモリでした。同じ重さならタングステンの方が小さいので、シャクリの跳ね具合、根がかりのしにくさ、キャストの飛距離とタングステンにアドバンテージがあります(ただし値段が数倍に…)。水深20m前後なら14g、18g、21gの3種類で対応できると思います。
<釣り方>
・アワセは小さく鋭くする
⇒ ワームを使ったブラックバスの釣りではストロークの大きなアワセを心がけていますが、今回はそれは逆効果でした。ストロークの大きなアワセ自体がダメなのではなく、アワセの後にラインを回収しないとファイトに入れないのがNGの要因です。魚に主導権を与えないためにも小さくて鋭いアワセ(+ハイギヤのリール)を心がけたいところです。
・バラした直後にルアーを回収しない
⇒ これはキャプテン指摘されるまで全く気付かない癖でした。フィッシュイーターは他の魚が食っているエサを狙っているため、また直ぐにヒットする確率が高いとのこと。「バラしたルアー=口から逃げたベイトフィッシュ」という認識ですね。確かに意識したらバラした直後に何回かヒットしました。
遠征釣行というと大げさに聞こえますが、LCC(ジェットスター)を上手く使えば、琵琶湖でバスガイドに乗るのと変わらないくらいの費用で普段とは別世界の釣りを満喫できます。
また、遠征や旅行の計画がない人もパックロッドを1本買うことで色々と行きたくなること間違いなしです。
僕がよく書くタキシード理論です。
> 「パーティーに呼ばれないから、タキシードを買わない」のではない
> 「タキシードを持っていないから、パーティーに呼ばれないのだ」
タキシードをパックロッドに置き換えると…
「遠征の予定がないから、パックロッドを買わない」のではない
「パックロッドを持っていないから、遠征の予定が立たないのだ」
遠征釣行に興味がある人はパックロッドとダッフルバッグを購入されることを強くおススメします。
関連記事:LCCを利用した格安釣り旅行のススメ
[パックロッドチャレンジ企画]現在の攻略状況(2016年9月現在)
1魚種目 : 鯉
2魚種目 : ブラックバス(スモールマウスバス)
3魚種目 : ニゴイ
4魚種目 : ナマズ
5魚種目 : ブラックバス(ラージマウスバス)
6魚種目 : ロウニンアジ(メッキ)
7魚種目 : マエソ
8魚種目 : クワガナー(コトヒキ)
9魚種目 : マングローブジャック(ゴマフエダイ)
10魚種目 : クロダイ(ナンヨウチヌ)
11魚種目 : イシミーバイ(カンモンハタ)
12魚種目 : ナガジューミーバイ(バラハタ)
13魚種目 : アカハタ
14魚種目 : アオヤガラ
15魚種目 : オジサン
16魚種目 : オキフエダイ
Posted by ueda at 07:00│Comments(0)
│釣行記(SW)



 アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト
アウトドア&フィッシング ナチュラムが提供する、自然と戯れ、自然を愛する人々のBlogサイト










![[シーバス]若狭湾・11/12-13・日本海シーバスにチャレンジ [シーバス]若狭湾・11/12-13・日本海シーバスにチャレンジ](http://img02.naturum.ne.jp/usr/p/m/a/pma/IMG_9932-s.jpg)